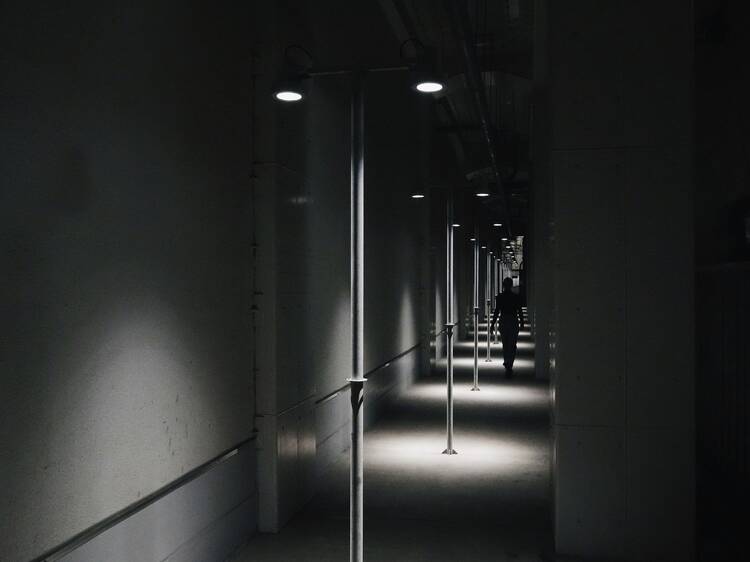都内の美大卒業後、ドイツ・ハンブルクでMFA取得。アーティストであり教授でもあるアンゼルム・ライラのもとで制作を行う。
美術評論家の松井みどりが提唱した、時代遅れや凡庸とされるものに新たな意味を与える「マイクロポップ」的な芸術表現や、スーザン・ソンタグが論じた、真面目に作られたがゆえに結果的にズレが生じて滑稽さを帯びる「キャンプ」的な美学に惹かれている。
とるにたらない日常に潜む断片を発見する眼差しを大切にし、制作者としての視点を記事に反映させたいと考えている。

都内の美大卒業後、ドイツ・ハンブルクでMFA取得。アーティストであり教授でもあるアンゼルム・ライラのもとで制作を行う。
美術評論家の松井みどりが提唱した、時代遅れや凡庸とされるものに新たな意味を与える「マイクロポップ」的な芸術表現や、スーザン・ソンタグが論じた、真面目に作られたがゆえに結果的にズレが生じて滑稽さを帯びる「キャンプ」的な美学に惹かれている。
とるにたらない日常に潜む断片を発見する眼差しを大切にし、制作者としての視点を記事に反映させたいと考えている。